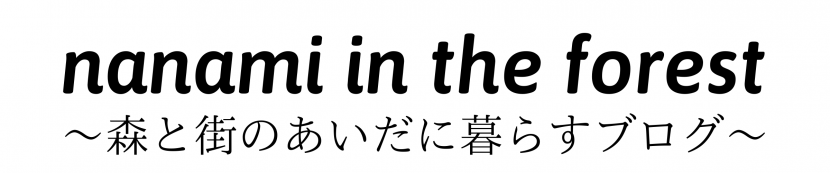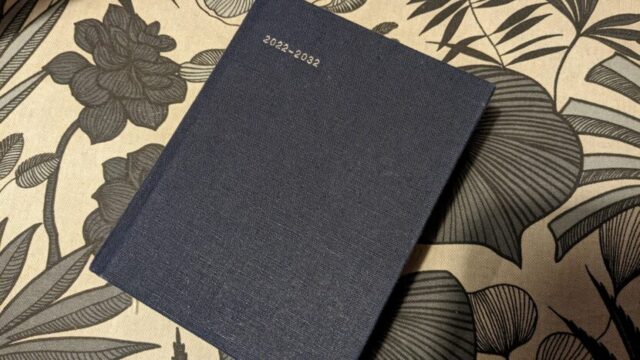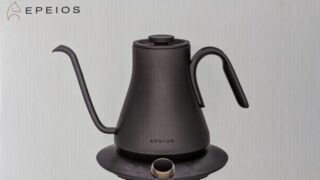40年以上前の話になります。
まだ、パティスリーとかパティシエなんて言葉、誰も使ってなくて、お店も人もまとめて「ケーキ屋さん」だったころ。
わたしが小学校の高学年だったある日、自宅から20分ほど離れたところ(通学路の途上)に、風変わりなお店が誕生しました。
オーボンヴュータン、というそのお店。
この名前からして、まず覚えにくくて。
昔は「ヴ」のつくお店なんてなかったと思う。
うちの親も近所の人も「えーと、オービューなんとかタン」みたいな感じで、いつまで経ってももうろ覚えという。
しばらくして「どうやらケーキ屋さんらしい」、とはわかったのですが、当時は、ケーキ屋さんと言えば白やパステルカラーが基調というのが当たり前の時代。
そんな中でオーボンヴュータンは、カーブを描いた入口のガラスが印象的で、中を覗くと、飴色のウッディなカウンターや棚の内装が、まるで行ったことないけど外国みたい。
敷居高い・・・
第一印象はそれです。
子どものみならず、うちの親だってそうでした。
まぁただ1度くらい行ってみようとおそるおそる、親子で行ってみると、見たこともないようなデザインのケーキが並んでいます。
何より驚いたのは値段。
当時から1つ350円から500円くらい。
さらに小さい!!
子ども心に最初に思ったのは、「なんでこんなに小さくて高い???」でした。(親もそう思ったはず)
まぁ、それもムリはなかったんです。
当時のメジャーなケーキ屋さんと言えば、まず不二家さんが筆頭というかほぼ一択。
メインとなるショートケーキはとっても大きくて、しかも180円でした(よく覚えてるな?)。
それが一種のモノサシだったので、比較して大きさは半分、値段は2倍、といった印象のオーボンヴュータンのケーキの意義が、子どもに理解できなくて当たり前でした。
というか大人でも理解できてなかったと思う。
しかも問題は値段だけではなく、そのどっしりとした味わいにもありました。
なんせ、それまで食べていた、ふわふわスポンジや軽い口当たりのクリームなどとは全然別物で、「ここにいるよ!」と言わんばかりの存在感。
お酒もそこそこ利いている感じがして、子どもも親も、「なんか…強いねぇ」としか表現できない、といった感じでした。
しかし、当時のわたし。
何度か食べるにつれて、
「なんか思ってたケーキとは違うけど、美味しい気がする」
と思ったんですよね。
(今思えば、ちょっとエラかった!)
値段が値段なのでごくたまに、ですが、買ってもらうようになりました。
この「なんか思ってたのと違うけど、なんかイイ」っていう感覚。
これって、時代の先を行っているものに出会ったときの共通のものなんじゃないか。
そんな気がしています。
記憶違いはあるかもしれないど、わたしの印象に残っているのは、ピラミッドの形をしていて、全体にチョコレートがかかっているケーキ。
中にはフランボワーズ(ラズベリー)のムースだかクリームだかが入っていました。
ベリーといえばイチゴしか知らなかった身にとって、その出会い自体が大きな革命でした。
で、そのまま人気店になるかと思いきや、そうではなかった。
オーボンヴュータンのお菓子はどれも「本格的なフランス菓子」。
逆に言えば、その当時の人々は、ほとんど見たことないものばかり。
「ケーキがいっぱいあっても、どれを選んでいいかわからない」
わけですよ。
しかも高いから、買ってみてハズレだったらイヤですよね。
やっぱり、味のわかってる不二家のショートケーキやチーズケーキが安心だよなぁ、という人が多かったと思います。
事実、毎日通学の行き帰りに店の前を通りますが、あまりお客さんが入っていなかった。というか、はっきり言えば、けっこうガラガラだった。
当時は、うちの親も含めて周りの大人は「あの店はすぐ潰れる」と言っていました。
しかーし、です。
お店はじんわりと続き、気づくとその地域の一番店になり、世田谷の一番店になり、やがて東京の…という具合に登り詰め、今では日本のフランス菓子のトップに君臨する店の1つです。
わたしはやがて実家を離れましたが、たまに帰るときに通りかかると、その度に客数が増えているような気がしていました。
いったい、何がどうなっていたのか。
その経過がオーボンヴュータンの創業者でオーナーシェフの河田勝彦さんの自著に書かれていました。
河田さんがパリへ修行へ行ったのは1967年。
横浜からソ連(現ロシア)へ船で渡って、そこからシベリア鉄道で約1週間かけてモスクワへ、さらに飛行機に乗ってフランスへ行った時代。気が遠くなる…
オーボンヴュータン開店当時の回想。
僕は、菓子で強い表現をしていました。だから菓子に対する客の反応はさまざまで、おいしいと言ってくれる人もいたし、お酒がきついとか、味がくどいとか言われたりもして……。売れるより、売れ残る数のほうが多くて、毎日ほとんど捨てていました。
やわらかい、ふわふわのショートケーキのほうが、日本人は好きなのかなあ。そのほうがお客さん受けがいいのかなあ、なんて考えても、僕には作れなかった。時代としては、スポンジのやわらかさや、生クリームのリッチさなどがもてはやされていました。
僕はほかの方法論を知らなかった。フランスで教わったことしかできなかったんです。
この本には、当時1億円もの借金をしてお店を構えたけれど、ケーキがさっぱり売れない日々が続いたことがさらりと書かれています。
まさにそれは、わたしやうちの親や近所の人々が、「なんか強いねぇ」「なんか高いねぇ」と言っていたあのころのこと。
潮目が変わった、今風に言えば「ブレイクした」のは開店から3年ほど経ったころ。
デパ―トへの出店依頼が舞い込み、さらにテレビで取り上げられてから爆発的な人気となり、知名度が上がっていったのだそう。
このことについて、河田氏は”「時代」のほうがふり向いた”、と表現されています。
わたしの実家もとうに引っ越してしまったので、先日、すごく久しぶりに立ち寄りました。
お店は数年前に移転(といっても前の場所からすぐのところ)していて、規模は数倍になっていました。

平日にも関わらず、開店前にはすでに10名ほどの列。
なんとかサロンの1回転目に入ることができました。
調度品とか、細かいところが「まんまフランス」です。
すごいこだわりを感じる。
でも子どもだったときは、この雰囲気が怖かったんですが(笑)

久しぶりに頂いたケーキ。
タルトってこういうもんか、と思いつつ、恐縮しながら頂きました。
小さい仕事がものすごく丁寧で、味は言うまでもありません。
左の「オペラ」は伝統菓子で、たぶん創業時からあったと思うのですが、昔食べたときには「なんか重くない??」って家族で首をかしげていたシロモノ。
チョコレートショートケーキと比べてしまっていたんですよね。
今なら、別格の美味しさがわかる。

内装にしても、味にしても、歳を取ったからわかることも多くて、珍しく加齢を喜んだのでした。
ところでさらに驚いたのは、値段がさほど変わってないように感じること。
500円のケーキと言えば、40年前は高くてビックリでしたが、今思えば当時は本格的な材料を調達することもすごく難しかったはずで、高くて当然です。
逆に今、このお店で500円台のケーキは、安すぎるくらい。
余談ですが数席あるサロンには、わたしと同じように「女性おひとり様」がちらほらいて、みんなケーキ3つとか食べてた(笑)
お菓子づくりをする人にとってはもちろん伝説の店なんですが、それにもまして「いつか時代がふり向くと信じて自分の道を歩きたい」と思うすべての人の生き方の指針になるような店だと思います。
80歳になろうという河田シェフ、今も現役で厨房に立たれるというから、もう尊敬しかありません。
店内の外装から内装から味からすべてがフランスそのものなので、プチフランス旅行みたいな気分を味わうにもおすすめです。
オーボンヴュータンとは、仏語で「思い出の時」という意味なのだそうです。
AU BON VIEUX TEMPS
オーボンヴュータン
東京都世田谷区等々力2-1-3
定休:火曜、水曜